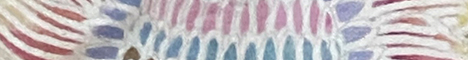私がやってみたいことの一つに、「古典模様への挑戦」がある。日本でBatikというと、3m近い長さの一枚布を身体に巻き着用するインドネシアの民族衣装カインパンジャン(大きい布の意味)など、ジャワ更紗の模様が描かれた布をイメージされる方が多いかもしれない。英語ではろうけつ染め技法のことをBatikという。現代ではろうけつ染め技法の一つとして、個人が自由に表現することができる。
私は今までシルクにロウ描きして草木染めする作品をメインに制作してきた。シルクと天然染料は相性が非常に良く、美しく素晴らしい色が魅力的で好きだった。それらに伝統的な模様を使用して自由な配色を楽しんできた。Batikの模様は摩訶不思議な世界で趣深く、カインソガン(紺茶配色のBatik)は2種類の染料で4色の色を表現するため、一見地味に見える布ではあるけれど、非常に複雑な配色計算がされていてバランスが良く構成されている。この複雑な布の奥深さはいつまで眺めていても飽きない。大好きではあるが、カインパンジャンサイズを描くだけの体力・精神力のない私なので、(なんせ表と裏にロウ描きしなければならないので)機会があれば描こうぐらいにしか思っていない。しかし、最近シルクの脱ロウが上手くいかなくなったので(これについてはまた別の機会に)、以前からモヤモヤしていたことをいよいよ中心に据えてやる時が来たと思い実践してみた。
オリジナルの模様をデザインして、伝統的なカインソガンの配色で実際に描いて形にしてみること。以前「葉唐草模様-Leaf arabesque-」をカインソガン配色で作った。カインソガンの制作行程については別の記事(カインソガンの作り方)をご参考ください。これは古典的なイセン(細かい装飾模様)を使用したシンプルな形状だったので配色計算は簡単だった。しかし、今回の「推し唐草模様」は自由度が高すぎていろんなバリエーションが考えられる。描き手の経験・センスにもよるだろう(イセンに顕著に現れる)。ロウ描きしながら改善点・変更箇所が出てきて、始めと終わりで違いが出てきた。それも良しと、自由なのだから。
伝統工芸として発展してきたBatikのカインソガン配色にはもちろんルールがある。たくさんの模様や描き手がいる中で、統一感がある理由である。新しい模様を考案した時には丁寧に配色を考える必要がある。それに従って作ったら、どの様に仕上がるのかをみてみたかった。図案を実際に描いてみてどんな雰囲気になるのか、絶妙な配色バランスになるのだろうか。最初の考えが足りず描きながら考えたりして、間違えるし変更したくなったりして常に変化していくダイナミックさを、現在進行形として体感したかったのだと思う。いつもカインソガンを描いている人より、私はまだ身体感覚としての配色はぎこちないだろう。しかもロウの温度も一定にキープしないとならないので、うーん、なんだかなぁと思いながら、まずは試行版のロウ描きを終えた。模様は連続して常に変化していく。次の行程は藍染めへ。続く。