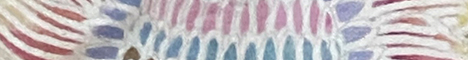このページではジャワ更紗を作る上で必要不可欠な道具、チャンティンとロウについてご紹介いたします。
1. ロウ描きをする道具 チャンティン
伝統的なバティックの多くは空間を隅々まで埋める細かい模様が特徴的です。主模様としての輪郭線(クロウォング)と、その主模様の意味を表し装飾する細かい模様(イセン)の2つの要素から成り立っています。これらを描く道具としてチャンティンが使われます。
チャンティンは、持ち手(ガガンテロン)となる竹と銅製部品の2つのパーツでできています。この銅製部品はすくったロウを溜める部分(ニャンプルガン)と、ロウの出口となる管先(チュチュック)、そして竹に差し込んで固定する部分で構成されます。この独特な形の部品がチャンティンらしさを体現しています。チュチュックの太さは、線の太さに比例します。インドネシアではこの道具を作る職人の数が減っているようです。クロウォングの線は太く、イセンの線はそれより細く描きわけることで、メリハリがある美しい模様を作ります。道具を上手に使用してきた人々の工夫に感嘆します。

▲銅製部分 左側からチュチュック、ニャンプルガン、差し込み部となる
さらに線を描くには、チュチュック先端に切り込み加工を施し、持ち手につけて使用します。切り込みを施すことで空気の入り口を作り、線の太さを一定に保つことができる重要な作業です。これは刃を使うので危険なため、熟練の技が必要です。購入した部品には施されていないので自分で加工する必要があります。最近は硬い真鍮製が出回っていますが、銅製の部品でないと加工できません。
また、チャンティンにはチュチュック形状により様々なバリエーションがあります。一度に2本の線が描けるチュチュックドゥアなど美しさやタイパを重視した個性的なものもあります。「描きたいものを表現するにはどうすればよいのか」という問いに対し、これらの存在が答えだと思う時、先人たちの試行錯誤が偲ばれます。
そして忘れられがちなのですが、道具のお手入れも大変重要です。長い間使用しているとロウの中に含まれる不純物が詰まって、線が綺麗に描けなくなってきます。定期的に掃除して大切に長く使用したいですね。
2. ロウ
ロウもまた、用途に合わせて使い分けされます。クロウォング・テンボックと呼ばれる2種類のロウを使い分けます。クロウォングのロウは、輪郭線・細かい模様・点々を描く時に使用します。サラッとしたロウはチャンティンが目詰まりすることなく、線や点を描くことができます。対してテンボックのロウは、広い面積を埋めるためのもので粘りけがあります。ロウの純度が高くなく、また現代のように空調設備がない時代、熱帯のインドネシアだからこそ発達した技法・道具といえます。
ロウ描きをする時は、ロウを電熱器で溶かします。鍋に一度にたくさん溶かさずに継ぎ足しながら使用します。ロウの温度は室温や気候に影響されますが、常に一定の温度に保つ必要があります。サーモスタッド付きの電熱器もありますが、それでは温度調整が大雑把すぎて使えません。「ロウが適温かどうかを見極める」この微調整は重要で、とても難しい技術です。そして電熱器に溶かしたロウは長時間使用していると煮詰まってくるため、時々鍋底に溜まる不純物を除去する必要があります。上手なロウ描きとは、ロウの温度とロウの状態を見極められるようになることでもあります。
忘れてはならないのはロウを外す作業です。脱ロウは完成一歩手前最後の作業です。せっかく作ったのにロウが付いたままではがっかりしてしまいます。インドネシアの古法では、お湯でとる方法とヘラで削ぎ落とす方法があります。今は石油系溶剤があるので簡単に落とすことができるようになりましたが、最近は環境への配慮や、伝統工芸産業の衰退で廃業するところも増えているようです。私はインドネシアのロウを使用していて、綿や麻生地は大体お湯で取れるのですが、絹地は石油系溶剤が不可欠なのでどんどん制作の幅が狭まっていきそうです。